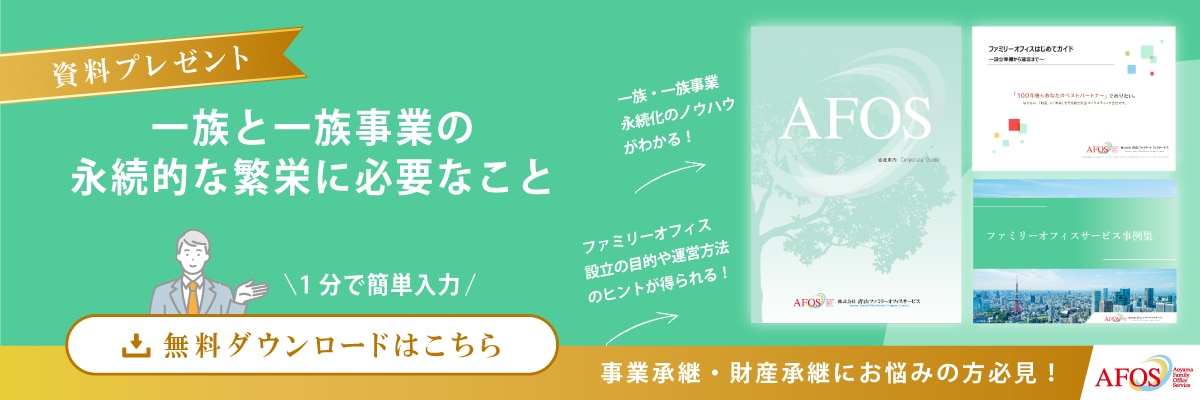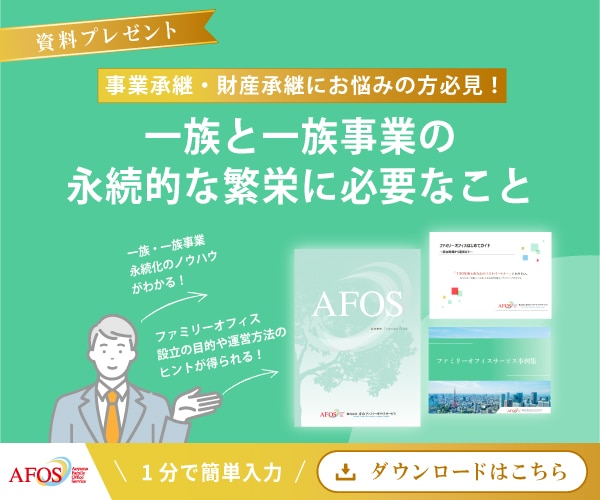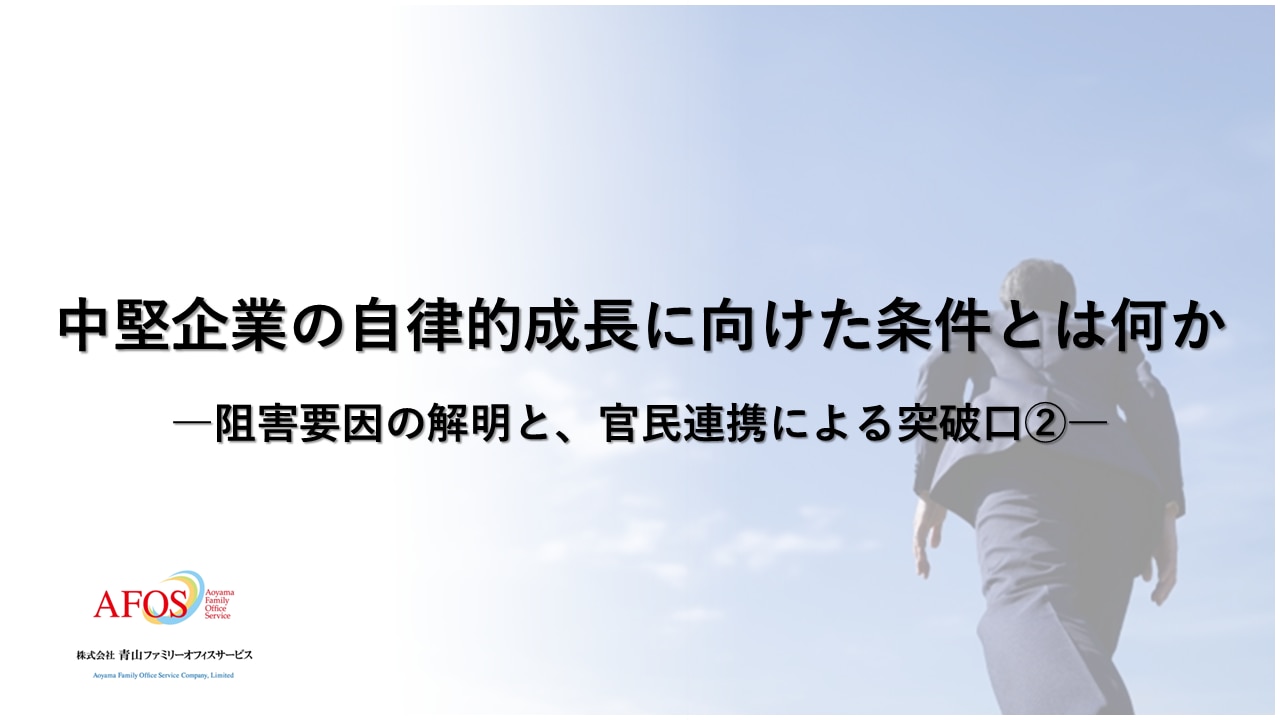
中堅企業の自律的成長に向けた条件とは何か ―阻害要因の解明と、官民連携による突破口②―
前稿「 中堅企業の自律的成長に向けた条件とは何か―阻害要因の解明と、官民連携による突破口①―」では、以下の中堅企業成長ビジョンの記載内容の活用をご提言した上で、内部環境課題にあたる(1)中堅企業の成長ビジョン・ガバナンスの必要性について取り上げました。
<前回ご提言した活用方法>
- 内部環境課題を述べている(1)中堅企業の成長ビジョン・ガバナンスの項を参考に自社の状況を点検する。
- その上で、外部環境課題を述べている(2)中堅企業を取り巻く伴走支援者のノウハウやマッチング制度を高度化・普遍化する仕組みに記載の、各種ノウハウやマッチング制度の活用方法を自社の経営戦略に落とし込む。
本稿では、(2)中堅企業を取り巻く伴走支援者のノウハウやマッチング制度を高度化・普遍化する仕組みに記載の政府が考える7つの外部環境課題を、政府の考える課題・原因・伴走支援者への期待・政府対応、に整理したうえで、そこから得られる示唆を検討していきます。
【参考資料】 ファミリーオフィスについて 下記ダウンロード資料もお使いいただけると、より実感を持って考えることができます! |
目次[非表示]
政府が考える「中堅企業が抱えている7つの外部環境課題」
①資金調達

政府の考える中堅企業の課題 | 資金調達のポテンシャルは高いものの、長期にわたる大規模投資等の非連続な成長機会への活用が不十分 |
原因 |
|
伴走支援者への期待 | 非連続な大規模成長投資の支援 |
政府の対応 |
|
<政府の考える課題>
中堅企業は、中小企業及び大企業と比較して無借金経営の企業が多く、高い資金調達ポテンシャルを有する。しかし一方で、海外展開やM&A、長期にわたる大規模投資等の非連続な成長機会の資金調達ポテンシャルが充分に満たされていないケースも存在する。
<原因>
- 金融機関を含む支援機関間の地域や国を超えた連携が未発達である。連携の未発達が原因で、中堅企業は最適なファイナンス手法や支援ノウハウを有するパートナーを選択できていない。最適な選択ができていない結果、中堅企業に支援機関から適切な提案や助言が行き届いていない。
- 上場中堅企業の場合、株主・投資家からの働きかけ(エンゲージメント)も成長のために有用になり得る。しかし現状、中長期の成長に貢献するエンゲージメント・ファンドは、規模・数ともに不足している。
<伴走支援者への期待>
金融機関・ファンド等が非連続な中堅企業の非連続な大規模成長投資を支援できるようになることが期待される。
<政府の対応>
❶以下の流れを創出し、幅広い企業の市場における資金調達を可能にする環境を構築
- 中堅・中小大規模成長投資補助金等を通じ、再現性ある中堅企業の成長経路モデルケースを創出
- 融資やファンドの活用も含めたファイナンス手法の高度化を図る
- 段階的に支援規模を縮小しつつ、幅広い企業が市場において資金調達が可能になる環境の構築を目指す
❷パートナーや提案内容のミスマッチを解消
補助金・税制・金融支援や地域円卓会議※等を活用しながら、政府系金融機関・民間金融機関・ファンド等の支援機関の間における適切な競争の下での協調を促す枠組みを構築する。
※地域円卓会議とは、多様な地域住民が参加し、地域の将来像を模索しながら、地域のために何ができるかを話し合う場です。地域の現状や課題を把握し、「地域づくり」への興味・関心を深めることを目的としています。参考: 地域円卓会議のススメ
❸中長期の成長に貢献するエンゲージメント・ファンドの規模・数の拡張
中堅企業に対して働き掛けを行う新興エンゲージメント・ファンドの創出・育成に向けてEMP※を推進する。
※EMPとは、Emerging Managers Program の略称であり、新興資産運用業者への運用資金拠出促進を図ることを目的としたプログラムを指します。
❹中堅企業に対し出資活用の後押し
PEファンドによる大規模M&Aや、事業の切り出し、オーナーによる買戻しを前提とした出資、地銀ファンドによる事業承継支援等の好事例を集約し、「エクイティ活用ガイドブック(仮称)」を作成する。
②人材確保

政府の考える中堅企業の課題 | 根強い人材不足のほか、大企業から中堅企業への人材の流れができていない点 |
原因 |
|
伴走支援者への期待 | 金融機関や人材仲介会社等の仲介機能向上により、経営人材及び専門人材が中堅企業へ継続的に流入する仕組みが定着すること |
政府の対応 |
|
<政府の考える課題>
中堅企業において、人手不足感は根強く存在している。また、大企業ではポテンシャル を十分に発揮し切れていない経営人材及び専門人材が中堅企業に移動して活躍できる余地は大きい。これらの背景にも関わらず、特に都市部から地方部への転居を伴う場合の大企業から中堅企業等への人材の流れが必ずしも大きくなっていない。
<原因>
- 中堅企業等の求人情報の掘り起こしやマッチングに手間がかかるために、人材仲介サービス、特に、単価が安い兼業・副業の場合のサービスの採算性が低く普及が進まない
- 求人企業と求職者が希望する賃金水準のギャップ
- 中堅企業等が成長ビジョンや人材投資方針等を十分にアピール出来ていない
<伴走支援者への期待>
資金の調達だけでなく、人材確保においても、日頃から中堅企業等の経営状況を理解した上で成長ビジョンの実現に必要な経営支援を行う、金融機関の役割が重要になる。金融機関や人材仲介会社等の仲介機能向上により、経営人材及び専門人材が中堅企業へ継続的に流入する仕組みの定着が期待される。
<政府対応>
❶中堅企業等の経営人材及び専門人材の獲得を後押しする事業を推進
一定規模の実績が蓄積されるまでの間、金融機関や人材仲介会社の、中堅企業等の経営人材及び専門人材の獲得を後押しする事業を推進。例えば、金融庁・経済産業省「 地域企業経営人材マッチング促進事業」、内閣府「 プロフェッショナル人材事業」「 先導的人材マッチング事業」、経済産業省「 地域の人事部支援事業」など
❷賃上げを伴う省力化投資のモデルケースを創出し、幅広い企業への普遍化を図る
具体的には中堅・中小大規模成長投資補助等で賃上げを伴う省力化投資のモデルケースを創出し、幅広い企業への普遍化を図り、現場人材も含めた足元の人手不足の課題に対応。
❸より多くの企業が人的資本経営の実践を通じて、魅力的な給与水準の設定や人材育成を含めた人材投資等を積極的に行い、労働市場等に情報発信することを後押し
- 賃上げ促進税制等による賃上げや教育訓練費増加に取り組む企業へのインセンティブ
- ジョブ型人事の普及
- 企業同士で議論や事例共有を行う人的資本経営コンソーシアムの活動を地域に拡大
❹地方における雇用の創出を後押し
具体的には、地方拠点強化税制等を通じた、企業の本社機能の地方移転や地方での拡充
③M&A

政府の考える中堅企業の課題 |
|
原因 | 買収先の価格のほか、リスク評価(デューデリジェンス)や売り手・買い手のマッチング、PMI サービスの価格などの調整不足 |
伴走支援者への期待 | M&A 後の成長を実現するようなサービス |
政府の対応 | インセンティブによる、買い手・売り手双方の生産性向上や賃上げ等の実現 |
<政府が考える課題>
M&Aは事業の成長、すなわち販路の拡大、人材や資産の獲得の有効な手段の一つだが、中堅企業が成長戦略として M&A を位置づけることは一般的になっていない。さらに、買収先企業とのシナジー効果を発揮する上での肝となる、買収後の経営方針や業務、企業文化の統合といったプロセス(以下 「PMI」という。)の実施は、わずかに留まっている。
<原因>
- 買収先価格、リスク評価(デューデリジェンス)や売り手・買い手のマッチング、PMI サービスの不相応の価格の提示
- M&Aを選択肢とする売り手側企業の不足
- 中堅企業へのファイナンスの問題
- のれんの定期償却による利益の下振れ
<伴走支援者への期待>
M&A 事業者(仲介会社や助言業務を行う会社)、PE ファンド、金融機関といった伴走支援者に、手数料の透明化、利益相反の禁止、経営者保証の解除等、健全な市場環境整備のために必要な事項に留意の上、M&A 後の成長を実現するようなサービスを期待する。
<政府対応>
❶インセンティブを通じて、買い手・売り手双方の生産性向上や賃上げ等を実現する M&A を後押し
具体的には、 中堅・中小グループ化税制などによりインセンティブを設ける。
❷買い手側・売り手側双方の課題の所在を明らかにしたうえで解決
具体的には、のれん非償却を含めた財務報告の在り方を検討。有価証券報告書で経営管 理上重要視する指標の開示事例を「 記述情報の開示の好事例集」として対外発信することを目指す。
当社のご支援事例はこちらから▼
④イノベーション

政府の考える中堅企業の課題 |
|
原因 | ー |
伴走支援者への期待 | ー |
政府の対応 |
|
<政府が考える課題>
中堅企業にとって研究開発や新事業展開は成長の重要な要素である。しかし、中堅企業は、研究開発や新事業展開に必要な人材・設備・技術等を自社で保有することは難しい。
他方、取引先、大学・公的研究機関、スタートアップや知的財産(以下 「知財」という。)・標準の専門家との連携に関して、中堅企業が成長段階に応じた適切なパートナーに巡り会えていない現状にある。
<政府対応>
❶イノベーション促進に資する税制の活用や具体的なイノベーション促進策の在り方の検討を進める
❷大学・公的研究機関との連携や研究開発プロジェクトへの参画を促進
❸新エネルギー・産業技術総合開発機構(NEDO)や産業技術総合研究所等の国立研究開発法人の中堅企業支援に関する中長期目標を設定
❹工業所有権情報・研修館(INPIT)や NEDO による知財・標準活動の助言等や、新市場創造型標準化制度の活用促進
(参考)
中小企業庁「 NEDOにおける中小企業支援に係る取組について」
中小企業庁「 産総研における中小企業関連の取組み」
独立行政法人工業所有権情報・研修館(INPIT)「 業務ご説明資料」
⑤海外展開

政府の考える中堅企業の課題 | 海外展開にる成長余地が大きい一方で、企業規模に対して高リスクな国際展開やM&Aに直面しやすい |
原因 | ー |
伴走支援者への期待 | ー |
政府の対応 |
|
<政府が考える課題>
海外売上比率が高い中堅企業は、労働生産性も高い傾向にある。更なる成長に向けては、輸出やインバウンドも含めて、海外需要向けのローカライズに対応しながら商圏を拡大し、企業価値を向上させていくことが重要である。
一方で、新規に海外顧客を獲得し、現地に生産・販売拠点も有していく段階になれば、特に、クロスボーダーのM&A、危険レベルの高い国への事業展開、海外ニーズ起点での新ビジネス創出等では、中堅企業の企業規模に比して大きなリスクを抱えることになる。
<伴走支援者への期待>
金融機関や商社といった伴走支援者は、中堅企業の現地での円滑な事業展開と資金調達
が図られるよう、自らのサービスの拡大とともに、日本貿易振興機構(JETRO)、日本貿易保険(NEXI)、国際協力銀行(JBIC)等の政府系支援機関とも積極的に連携していくことを期待する。
<政府対応>
❶日本貿易振興機構(JETRO)等、海外展開支援をミッションに掲げる独立行政法人に対して中堅企業支援に関する中期目標を設定
❷JETRO におけるハンズオン支援の対象となる中堅企業の範囲の拡大
❸日本貿易保険(NEXI)は貿易保険メニューを中堅企業向けに拡大
❹国際協力銀行(JBIC)は、成長に資する国内の中堅・中小企業の海外展開について、地域金融機関とともに支援
❺グローバルサウス未来志向型共創事業等による海外市場開拓や、海外で事業を展開する中堅企業を先導役として、関連中小企業にノウハウを共有しながら共に海外展開を図る取組を推進
⑥専門家活用

政府の考える中堅企業の課題 | 中堅企業ならではの多様で高度な経営課題に直面するも、ニーズに合った専門的なコンサルティングサービスが普及していない |
原因 | 中堅企業が軸足に置く地方における専門的なコンサルティングサービスの過疎化 |
伴走支援者への期待 |
|
政府の対応 |
|
<政府が考える課題>
中堅企業は、規模が拡大するにつれて業態や展開地域が広がり、経営課題の幅も、金融、人材マネジメント、GX、DX、M&A、マーケティング、研究開発など、広範かつ高度なものとなり、それぞれに最適なコンサルタントや弁護士、会計士といった専門家を活用していく必要がある。
しかし、このようなコンサルティングサービスは大企業向けには充実しているが、中堅企業のニーズに合う程度のサービスが提供されておらず、ミスマッチが生じている。
<原因>
専門家が都市部に集中、一方で、中堅企業は経営の軸足を地方に置く割合が高いがゆえにアクセスが限られる。
<伴走支援者への期待>
中堅企業が求める成果に見合う報酬でのサービスを提供することや、ハンズオン型のファンドに代表されるように、中堅企業に出資等の形で関与し、経営改革の実践を通じて企業価値を上げて報酬を得る成果連動型のサービスの拡大が期待される。
<政府対応>
地域円卓会議を起点とし、地域特性と多様な業種及び課題に対応できる専門家のネットワークを構築する。
地域特性に応じた適切なKPI を設定し、中堅企業からの評価や企業価値向上の実績を蓄積し、一定の能力を有する専門家を可視化することで、ユーザー側の視点が専門家サービスに反映される自立的なサイクルを確立。
⑦GX・DX

政府の考える中堅企業の課題 | GX・DXへの適応力を有する一方で、GX・DX推進人材・ノウハウが不足 |
原因 |
|
伴走支援者への期待 | ー |
政府の対応 | GX・DX推進 |
<政府が考える課題>
中堅企業は、GX・DX 等の事業環境の変化に柔軟に適応するポテンシャルを有するものの、GX・DX を推進する人材・ノウハウが足りていない等の課題から、取組が進みづらい傾向にある。また、サプライチェーンによっては、脱炭素の取組やデータ活用・管理の体制等が取引先から求められることもあり、こうしたリスクに直面する企業を中心として、対応策を講じていく必要がある。
<原因>
企業の意識向上が途上であることや、専門人材が不足している。
<政府対応>
『GX推進』
- エネルギー消費量やCO2排出量の算定・見える化のための国の電子報告システムの改修
- 省エネルギー・省CO2を促進する設備導入支援
- 地域におけるプッシュ型の支援体制の構築
『DX推進』
- DXによって企業価値が向上した先進事例の選定
- 中堅企業等と支援機関双方の優良事例の増加
- 民間や大学等のデジタル教育コンテンツの一元化や実践的な教育プログラムの提供
- 個人のデジタルスキル情報を蓄積・可視化する仕組みの整備
中堅企業成長ビジョンが指摘する7つの外部環境課題から得られる示唆
中堅企業成長ビジョンでは、中堅企業には「成長余力」、「変化余力」、「社会貢献余力」の3つの余力があることが示されています。「余力がある」との指摘は期待が込められていると同時に、「現状はポテンシャルが最大限発揮されていない」との指摘と同義とも言えます。
本稿では、中堅企業成長ビジョンにおける政府が考える7つの外部環境課題に関する記述を整理して概観した結果、中堅企業と外部環境資源との間に存在する様々なミスマッチに関する指摘が確認されました。
政府によるこのミスマッチの指摘と中堅企業の自律的成長環境が不十分との問題意識を照らし合わせると、法的に「中堅企業」区分を設けるにいたった「中堅企業特有の経営課題に対する目配りが欠け、適切な政策支援も不十分になっている状況」の結果こそが、このミスマッチであると考えられます。
つまり、この「中堅企業と様々な外部資源とのミスマッチの解消」こそが、中堅企業成長ビジョン、つまり中堅企業の自律的成長環境整備の大きな方向性と言えるのではないでしょうか。
(まとめ)<中堅企業が抱えている7つの外部環境課題>
- 経営課題に対する目配り
- 適切な政策支援が不十分・資金調達
・人材確保・M&A
・イノベーション・海外展開・専門家活用・GX・DX
(まとめ)<中堅企業の3つの余力>
- 成長余力
- 変化余力
- 社会貢献余力
「中堅企業成長ビジョン」に関するシリーズ記事全体を通して
本シリーズではこれまで4回にわたり、中堅企業成長ビジョンを読み解き、政府が、
① 2024年を「中堅企業元年」と位置づけ、中堅企業向け支援を体系化すること、その中で中堅企業の過半を占めるファミリービジネスの特徴を公式に再評価したこと
( 中堅企業元年-中堅企業政策に見るファミリービジネスへの再評価)
② 「中堅企業成長ビジョン」で設定したKGI(付加価値年率4%成長)と3つのKPIを通じ、中堅企業―とりわけ多数を占めるファミリービジネス―を日本経済の「価値創出の主体」に据え、今後の支援策を“戦略的投資”として動員しようとしていること
( 中堅企業成長ビジョンのKGI・KPIに見る、政府のファミリービジネスへの期待と、ファミリービジネスとしての活用)
③ 中堅企業の“自律的成長”環境実現には外部の資金・人材・伴走支援等とのミスマッチの解消が必要であり、そのために中堅企業の内部施策として「①長期の成長ビジョン」と「②それを支えるコーポレート・ファミリー双方のガバナンス」整備が重要であると考えていること
( 中堅企業の自律的成長に向けた条件とは何か―阻害要因の解明と、官民連携による突破口①―)
④ 中堅企業と外部資源との間には様々なミスマッチが存在し、7つの外部環境課題ごとに、このミスマッチ解消のための施策を打ち出す方針であること(本稿)
を確認してきました。
それでは、今まで確認してきたこれらの内容から、ファミリービジネスの経営者や、ファミリービジネスに関わるアドバイザーが得られる示唆にはどの様なものがあるでしょうか。
2014年から2025年までサントリーHDの社長を務めた新浪氏は、IMDのインタビューで、サントリーの120年以上にわたる「創業精神」に立ち返り、品質への執着や挑戦・リスクテイク、労働者との強い関係等の重要性について語ると同時に、「コミュニティがビジネスチャンスを与えてくれるのだから、まず社会に還元しなければならない」と語り、社会との対話を重んじる姿勢を示しています。(参考:IMD 「CEOインタビュー:Suntory’s growth from Beam integration offers lessons in collaboration and adherence to core values
」)
ファミリービジネスは、創業家固有の理念と価値観に基づき、公平な利益分配を世代横断的に継続できる構造を持ちます。そして、この構造こそが、外部の有形・無形資産との強固な協調関係を築き、ビジネスの最大の強みとなると考えられています。
今、中堅ファミリービジネスに問われているのは、このファミリービジネスの理念・価値観をベースした超長期的な一貫した振舞いと、その結果としての内外の経営資源のネットワーク化という特徴を、より大規模かつ透明性を持って継続するための仕組みをいかに構築するのか、ということではないでしょうか。
この考えに立つと、ファミリービジネスの経営者とアドバイザーが取るべき実践手順として、①創業理念と社会課題を結び付けたパーパスを掲げかつ具体的KPIに落とし込み、②統合報告書や地域説明会等で外部に発信し、③共感を軸に資金・人材・技術のパートナーシップを形成する、といったことが考えられます。
こうした取り組みは、政府の、中堅企業支援施策の対象を成長志向の企業に重点化する方針を明確にし、支援企業の取組や成長ビジョンを広く社会に対して情報発信するとともに、企業がこれらステークホルダーと円滑に対話するための環境を整備する、との方針とも整合的です。
これからは、ファミリービジネスとしての自然な振舞いを高度化した企業に対し中堅企業施策の後押しがなされる環境が整備される、と捉えることができ、今後ますますファミリービジネスの持つ特色への評価が高まることでしょう。
本シリーズでは4回にわたり、「中堅企業成長ビジョン」から再評価されるファミリービジネスの特徴を確認し、その更なる発展のための示唆を探ってきました。本シリーズが、ファミリービジネスのオーナーや経営者様のファミリービジネスであることの誇りと、ビジネスとご一族双方の発展に僅かながらお役に立てば幸いです。
【参考資料】 ファミリーオフィスについて 下記ダウンロード資料もお使いいただけると、より実感を持って考えることができます! |